このたび標記について、健康保険法施行令等の一部改正が行われ、平成21年1月1日から施行されることになりましたので、その具体的な内容について下記のとおりお知らせします。 |
|||||||||
| 1.産科医療補償制度の創設 | |||||||||
| (1)概要 | |||||||||
| 出産による事故で、生まれた子供が障害を抱えた場合、家族や子供を救済するための補償制度「産科医療補償制度」が平成21年1月1日から始まります。 今回の改正に基づき、出産した被保険者等に支給している出産育児一時金の現行法定給付額を下記2.のとおり3万円引き上げ、この補償制度の原資にすることになります。 |
|||||||||
| (2)補償の内容等 | |||||||||
| ① | 補償の対象となる事故 | ||||||||
| 通常の妊娠・出産だったにもかかわらず、原則として妊娠33週以降かつ体重2000g以上で生まれた子供が重度の脳性まひになったとき。(未熟児として生まれた場合や、検査でわかる遺伝子異常など先天的な原因によるものは対象外。) | |||||||||
| ② | 補償額 | ||||||||
| 対象となった子の看護・介護のための一時金として600万円、分割金として年120万円(月10万円)が20年間に渡って支給されます。 | |||||||||
| ③ | 制度の運営 | ||||||||
| ㈶日本医療機能評価機構が運営し、同機構と損害保険会社6社で作る保険に、出産を扱う医療機関が加入し、1出産につき3万円の掛け金を支払うことになります。 | |||||||||
| ④ | 医療機関が同制度に加入しているかどうかの確認について | ||||||||
|
|||||||||
| ⑤ | 「産科医療補償制度登録証」で登録 | ||||||||
| 制度に加入している医療機関で出産する場合は、医療機関から「産科医療補償制度登録証」(控え)が交付されます。万が一の場合は1年後に補償金の申請を行うので、この登録証は母子手帳に挟み込むなどして大切に保管いただくことになります。 | |||||||||
| ⑥ | この制度の詳細については、上記の㈶日本医療機能評価機構のホームページの産科医療補償制度のサイトをご覧ください。 |
||||||||
| 2.健保組合の給付 | |||||||||
| (1)出産育児一時金等の支給額の改正(平成21年1月1日出産から適用) | |||||||||
| ① | 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合 ⇒38万円(3万円引き上げ) | ||||||||
| ② | 産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合⇒35万円(変更なし) | ||||||||
| ③ | 在胎週数第22週より前に出産した場合 ⇒ 35万円 | ||||||||
| (2)出産育児一時金の申請における産科医療補償制度への加入の確認方法 | |||||||||
| ① | 事後申請の場合 | ||||||||
| 産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合は、「出産育児一時金請求書」に、当該医療機関が同制度に加入していることを証明するスタンプが押された領収書の写しを添付いただくことになります。なお、この領収書の写しの添付がない場合、またはスタンプのない領収書の写しが添付された場合の法定給付は35万円となります。 | |||||||||
| ② | 受領代理人を利用する場合 | ||||||||
| 出産後、当該医療機関から出産費用の請求書が当組合へ送付されますが、その請求書に上記スタンプが押されることになります。 | |||||||||
| (3)その他 | |||||||||
| 当組合が独自に給付している付加給付10万円は従来どおり給付されます。 | |||||||||
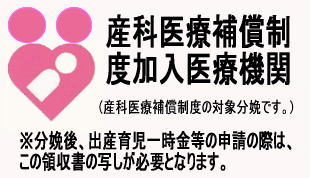 |
|||||||||
| スタンプのイメージ | |||||||||